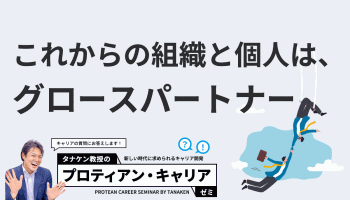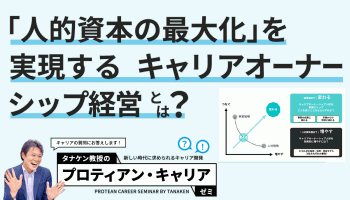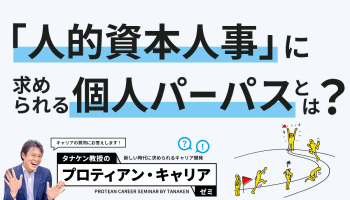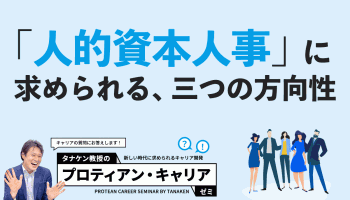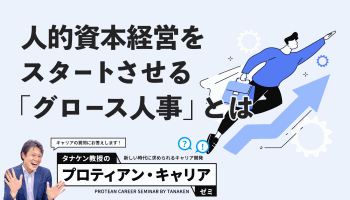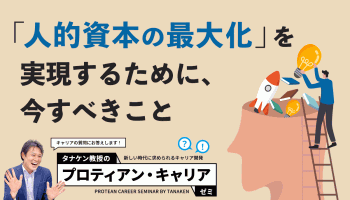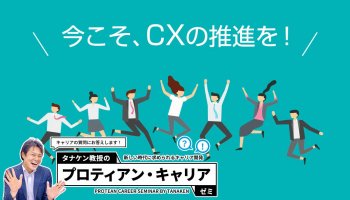「タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ」関連のコンテンツ
タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第31回】
これからの組織と個人は、グロースパートナー
これまでの日本型雇用は、組織内キャリアを前提としていました。終身雇用を前提とすることで、組織側のタイミングで人事発令や全国への転勤が行われ、副業は禁止とされてきました。しかしコロナ・パンデミックを経て、明らかに働き方の歴史が変わりました。組織内キャリアから自律型キャリアへのトランスフォーメーションが...
タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第30回】
「人的資本の最大化」を実現するキャリアオーナーシップ経営とは
なぜ、キャリア自律なのか? 答えはシンプルです。組織内キャリアでは、組織も個人もグロースしないからです。プロティアン・キャリアとは「関係論的アプローチ」を大切にしています。個人と同僚、個人と組織、個人と社会など、さまざまな関係性をより良いものに構築していくためのキャリア自律なのです。
タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第29回】
「人的資本人事」に求められる個人パーパスとは?
今、求められているのは、人的資本人事です。まず、大前提として共有したいのは、組織における「人材」は費用=コストではないということです。人材版伊藤レポートでも触れられているように「人材」ではなく、「人財」なのです。つまり、社員一人ひとりは経営のコストではなく、投資対象なのです。
タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第28回】
「人的資本人事」に求められる、三つの方向性
これからの人事部は、組織の管理部門を担うだけではなく、組織の成長部門をけん引するチームでなければなりません。人材版伊藤レポートでもすでに指摘されているように、日本企業の人事部が抱える特性であり、「弱点」であるといえるでしょう。グローバル企業と比較しても、管理部門としての人事の役割は突出しています。
タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第27回】
人的資本経営をスタートさせる「グロース人事」とは
2022年に私が取り組んでいきたいことは、人事部門の役割転換です。具体的には、人事の役割を管理・調整・配置などのディフェンシブな管理機能から、成長・開発・抜擢などのオフェンシブな成長機能へと転換させていきたいと考えています。
人的資本、ISO30414、ダイバーシティ、リーダーシップ、生産性、キャリア、タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ
タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第25回】
「人的資本の最大化」を実現するために、今すべきこと
今、企業が早急に取り組むべきなのは、「人的資本の最大化」です。超少子高齢化による慢性的な労働人口不足に加えて、コロナ・パンデミック対応による「鎖国状態」。人材不足が深刻化していますが、そのための解決策は主に四つあります。
人的資本、キャリア開発、キャリア自律、プロティアン・キャリア、パルスサーベイ、タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ
タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第24回】
働くことをアンラーニングせよ:フランケンシュタイン? それとも、創意工夫?
私たちは今、未来の歴史の教科書に掲載される日々を過ごしています。コロナ・パンデミックにより、これまで前提としていた都市集中型の対面労働が大きな転換を迎えているからです。
タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第23回】
「組織内エンゲージメントの向上」と「主体的なキャリア形成」の両立は可能! その根拠とは?
「社員のエンゲージメント向上」「社員の主体的なキャリア形成の支援」に取り組んでいる人事の方は多いでしょう。一方で「組織内エンゲージメントを向上させながら、主体的なキャリア形成を支援する」「主体的なキャリア形成を支援しながら、組織内エンゲージメントを向上させる」の両立に取り組む企業は多くありません。
エンゲージメント、キャリア形成、アンコンシャス・バイアス、エンゲージメントサーベイ、タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ
タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第22回】
やめよう「アドオン人事」――「戦略人事」の「戦略」に、いま求められているものとは?
戦略人事という考え方は、広く受容されています。実際に『人事白書2021』の「戦略人事は重要である」という設問に対して、「当てはまる」(55.8%)、「どちらかといえば当てはまる」(35.2%)と合わせて91.0%という高い認識が回答されています。
タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第21回】
これからのキャリア開発:「スキル見直し研修」から「キャリア開発研修」へ
これからの組織に必要なのは、経営戦略、事業戦略、キャリア戦略、この三つの戦略を連関させながら社会変化に適合させ、生産性と競争力を高めていくことです。このキャリア戦略の重要部分を占めるのが、育成施策です。
タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第20回】
今こそ、CX(=キャリアトランスフォーメーション)の推進を!
DX(Digital Transformation/デジタルトランスフォーメーション)の推進には、CXが欠かせません。CXとは、Career Transformation/キャリアトランスソーメーションを意味します。CXの推進の目的は、人々の働き方や生き方をより良いものへと変革させることです。なぜ今...
DX、デジタルトランスフォーメーション、CX、キャリアトランスフォーメーション、セルフキャリアドック、キャリア自律、プロティアン・キャリア、タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ